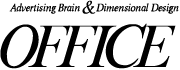地域と農家をつなぐ、進化した無人販売所のデザイン事例
2025.06.13 WORKS

農村地などでは昔から親しまれてきた「無人販売所」。多くはりんご箱や簡易な屋根を用いた素朴なスタイルで、農家が自らの野菜や果物を直接消費者に届けるための手段として利用されてきました。しかし、浜松市内に約10カ所の無人販売所を展開する依頼主からの今回の依頼は、従来とは異なる新しいアプローチを求めるものでした。目的は、単なる陳列台ではなく、「見た目」「機能性」「安全性」を兼ね備えた現代的な無人店舗の開発です。
高機能な構造とこだわりの設計
今回開発された無人販売店舗は、まず仕様の確認と設計から丁寧に行い、金属板を用いた板金加工を実施。全体にサビ止め塗装を施すことで耐久性を高め、屋外環境に強い構造としました。さらにキャスターを取り付け、必要に応じて自由に移動できるようにしたことも大きな特徴です。
また、天候の影響から商品を守るために、しっかりとした屋根と壁面を備えた設計とし、雨風への強さを確保。これにより、年間を通じて安定した運用が可能になりました。
販売者と利用者に優しい工夫
機能面においても細かな工夫が施されています。例えば、販売対象となる商品の種類に応じて棚の高さ(ピッチ)を柔軟に変更できるよう、細かく設定可能な可変棚を導入。さらに、高齢者にも使いやすいよう、全体の高さも配慮されて設計されています。
また、販売者側ではキャッシュレス対応として「PayPay」の導入を実施し、利便性を向上。加えて、防犯対策も行うことで、安心して商品を購入できる環境が整えられています。
店舗との連携による集客効果
設置場所にも工夫がなされており、通行量の多い道路に面した清潔感のある店舗と契約。その前に無人販売台を設置することで、既存の店舗利用者が「ついで買い」しやすい導線を生み出しています。この戦略により、農家にとっては販売機会の拡大、店舗にとっては新たな集客手段となり、双方にとってメリットのある仕組みが形成されました。

地域に根ざした新たな交流の場へ
こうした取り組みの結果、実際に利用した地域住民からは「使いやすくて見やすい」「きれいで安心して購入できる」といった好意的な声が多く寄せられており、農産物の購入をきっかけとした新たな地域交流の場としての役割も果たし始めています。
このように、地域資源を活かしながらも、現代のニーズに応じた無人販売店舗のモデルは、今後の農業のみならず地域活性化においても非常に有望な取り組みとして注目されています。